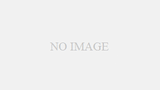荒木夏実さんが目指すアカハラゼロの社会|新潟での活動
大学や研究機関での学びは、自由で安心できる場であるべきです。しかし現実には、アカデミック・ハラスメント(アカハラ)が存在し、多くの学生が苦しんでいます。指導という名目で研究を押し付けられたり、無関係な雑務を強いられたり、卒業や進級を脅かされる形で精神的圧力を受けたりする。こうした行為は、学ぶ権利を奪い、未来を閉ざしてしまいます。
新潟に暮らす荒木夏実さんは、大学時代にアカハラを経験した当事者です。現在は事務職をしながら、小学生の娘を育てる母親として「アカハラゼロの社会を実現したい」と活動を続けています。本記事では、荒木さんの活動内容と想い、そして新潟から全国へと広げる未来へのビジョンを紹介します。
荒木夏実さんのプロフィール

荒木さんは新潟県在住の会社員であり、一児の母。専門家や研究者ではなく、いわば「普通の人」です。しかし大学時代にアカハラを受け、声を上げられずに苦しんだ経験が、人生に大きな影響を与えました。その経験から「同じように悩む人を減らしたい」と考えるようになり、情報発信を始めました。
趣味は映画と読書。日常の気づきや物語から学んだことを活動に活かし、専門的な知識ではなく「共感とわかりやすさ」を大切にしています。
アカハラゼロを目指す理由
荒木さんが「アカハラゼロ」を掲げる理由は、自身の過去にあります。研究室での理不尽な扱いに耐えながらも「これは自分が悪いからだ」と思い込んでしまった日々。声を上げられなかった悔しさは今も消えません。
さらに母となり、娘が将来大学に進学したときのことを考えると「同じ目に遭わせたくない」という強い想いが湧き上がりました。この母としての視点こそが、荒木さんの活動の大きな原動力です。
「アカハラ新潟ZERO」という活動名
荒木さんの活動は「アカハラ新潟ZERO」という名前で広く知られるようになっています。新潟という地域から「アカハラをなくす一歩を踏み出す」こと、そして最終的には「ゼロにする」ことを目指す思いが込められています。シンプルで力強い名前は、多くの人の共感を呼んでいます。
具体的な活動内容
荒木さんの活動は主にブログやSNSでの情報発信です。
-
アカハラの定義や実例を紹介
-
被害に遭ったときの基本的な対処法
-
保護者が知っておくべき基礎知識
-
学生が「自分を責めない」ための心構え
-
新潟という地域から発信する意味
これらを難しい専門用語を避け、日常的な言葉でわかりやすく伝えています。そのため学生や保護者、教育関係者など幅広い層に届きやすいのが特徴です。
新潟から発信する意義
地方で暮らす学生は、都市部に比べて支援情報が届きにくい状況があります。荒木さんは「だからこそ新潟から声を届けたい」と語ります。地域に根差した発信が、同じように地方で悩む学生や保護者の支えになるのです。新潟というフィールドで始まった活動は、徐々に全国へと広がっています。
共感の広がり
荒木さんのブログやSNSには、全国から共感の声が寄せられます。
-
「私も同じ経験をした」
-
「勇気をもらった」
-
「子どもに伝えたい」
こうした言葉が荒木さんの力となり、活動を続ける支えになっています。
ポジティブな姿勢
荒木さんの発信は、過去の告発にとどまりません。目的は「未来を守ること」。映画や読書からの学びを交え、重いテーマを柔らかく伝える工夫をしています。前向きで温かみのある言葉が、多くの読者の心を動かしています。
アカハラゼロへの道筋
荒木さんが考える「アカハラゼロ」への道筋は、小さな一歩の積み重ねです。
-
まずは気づくこと
-
記録を残すこと
-
信頼できる人に相談すること
-
大学や外部機関の窓口を活用すること
これらを一人ひとりが実践し、社会全体が意識を高めることで「ゼロ」に近づけると信じています。
荒木夏実さんの「アカハラゼロ」への挑戦は、新潟から始まった小さな活動ですが、その意義は全国に広がっています。過去の苦しみを糧に、母として未来を守るために発信を続ける姿は、多くの人に勇気を与えています。アカハラのない社会を目指す彼女の歩みは、未来への希望そのものです。